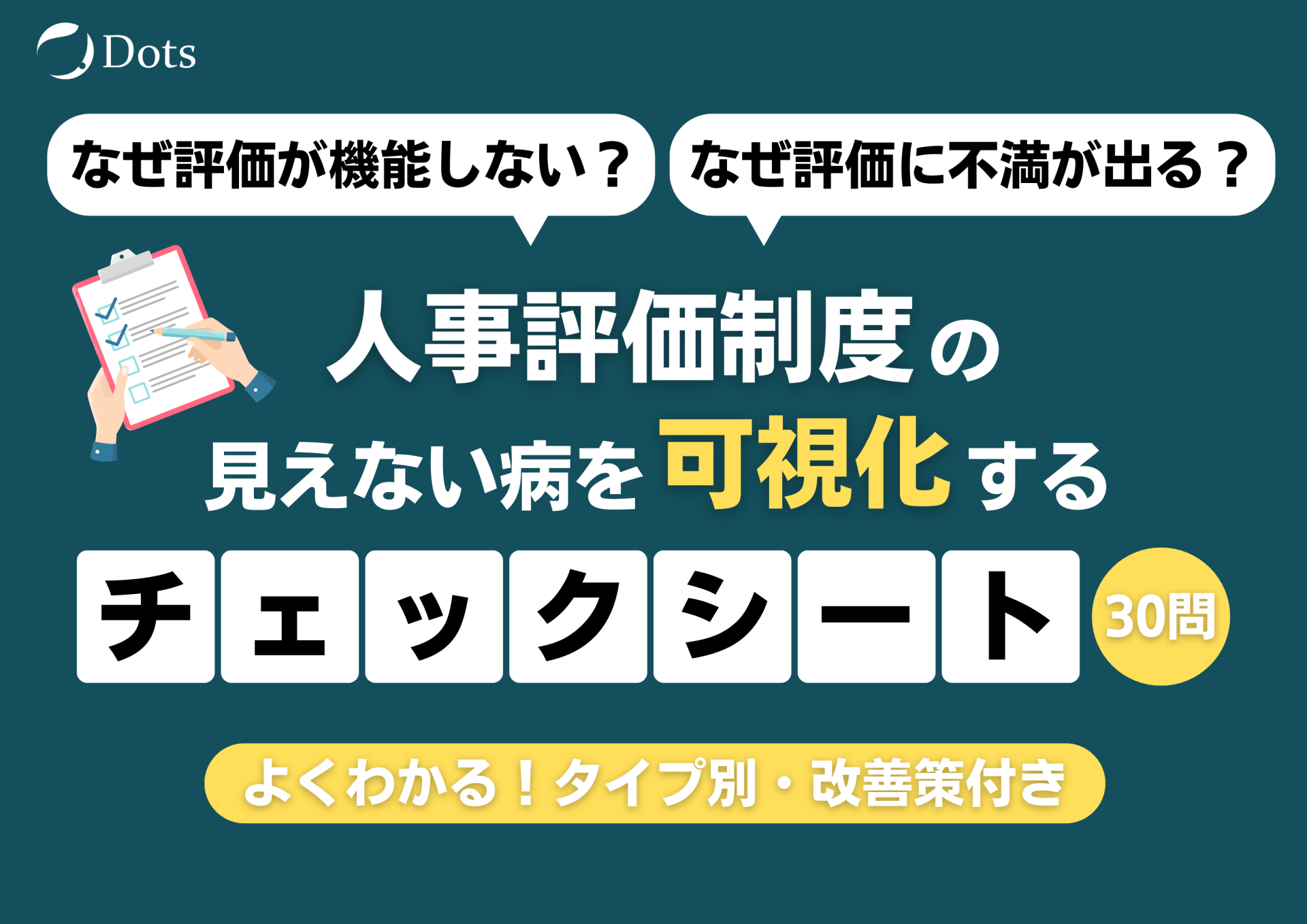【最大30%削減事例も】社員満足度と離職率の関係とは?─ 中小企業・人事担当者向け 実践ガイド ─
ブログ
2025.10.22
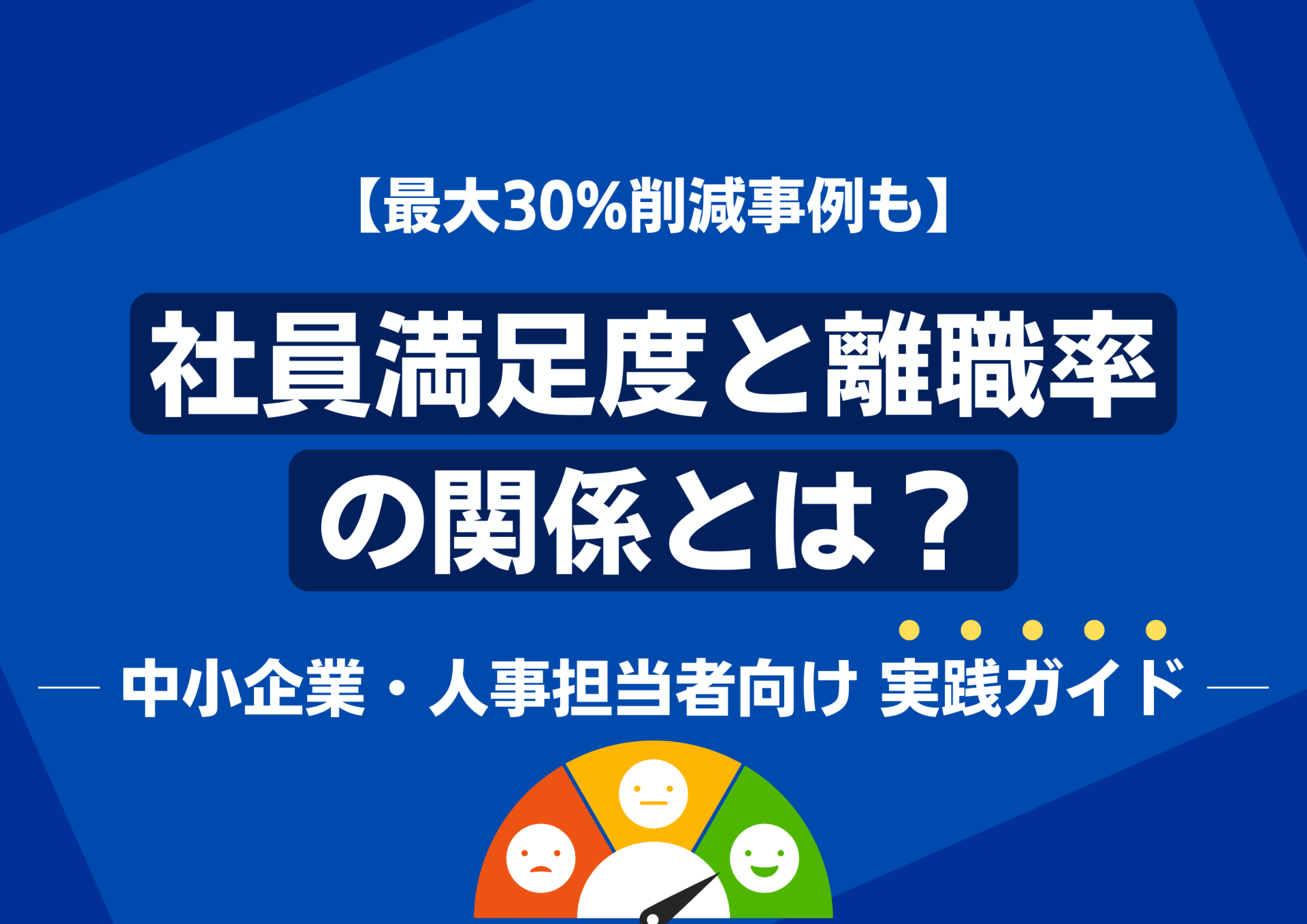
「せっかく採用した優秀な社員が、なぜかすぐに辞めてしまう。」
そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか?
現代企業にとって、採用コストや育成コストはますます重くのしかかっています。優秀な人材を採用できても、彼らがすぐに離れてしまっては、企業にとって大きな機会損失となります。
その根底にあるのが、社員満足度と離職率の密接な相関関係です。
社員が自社に満足しているかどうかは、彼らが「ここで働き続けたい」と思うかどうかに直結します。
本稿では、以下の流れでこの関係性を解き明かしていきます。読み終えた時には、「自社でどこから手をつけるべきか」が明確になるはずです。

社員満足度と離職率の関係:定義と理論構造
社員満足度(ES:Employee Satisfaction)とは?
社員満足度とは、従業員が職場環境や待遇、成長機会、制度、組織のあり方などに対して感じている「満足感」「納得感」を意味します。主に以下の要素で構成されます:
- 給与・賞与・福利厚生への納得性
- 仕事内容の意義や成長の実感
- 上司・同僚との人間関係やコミュニケーションの質
- 評価制度・昇進制度の透明性と公平性
- 働き方の柔軟性(リモート、フレックス、時短など)
- 健康支援・メンタルケア制度の充実度
測定手法としては、定量評価(5〜7段階リッカート尺度)やNPS(推奨度)調査、自由記述やクロス集計などがよく使われます。
離職率とは:算出方法と実態データ
離職率は、以下の式で計算されます:
離職率 =(期間中の離職者数 ÷ 期間中の在籍社員数) × 100(%)
厚生労働省「令和5年 雇用動向調査」によると、日本全体の平均離職率は15.4%です。
ただしこれは業種・企業規模・雇用形態によって大きく異なり、自社内比較が重要です。
出典:従業員満足度調査に関する調査2024—NTTコム リサーチ
満足度と離職率の相関理論モデル
社員満足度と離職率の関係は、次のような因果構造で説明できます:
- 満足度の向上 → エンゲージメントの上昇
- エンゲージメント上昇 → モチベーション・仕事への没入感の増加
- 成果と貢献の実感 → 組織への信頼と帰属意識の強化
- 帰属意識の持続 → 離職意向の抑制 → 離職率の低下
※もちろん例外として、満足していても家庭事情やキャリアチェンジ志向などで離職するケースもありますが、このモデルは組織的な離職抑制施策の基本指針となります。
離職率が高くなる主な原因:構造的視点で分析
以下は、離職を引き起こす代表的な要因をカテゴリ別にまとめたものです。
| 原因カテゴリ | 典型的な課題 | 主な影響 |
| 過重ストレス・業務負荷 | 残業の常態化、不明瞭な指示、業務の属人化 | 疲労蓄積・燃え尽き症候群 |
| 評価制度・昇進制度の不公平性 | 主観評価・透明性欠如・昇進枠不足 | 成果への信頼喪失・不満増大 |
| 柔軟性の欠如 | リモートワーク制限、通勤負担、固定勤務 | ワークライフバランス悪化 |
| 成長機会不足 | 研修機会の欠如、自己開発の支援不足 | 将来展望が持てず離職へ直結 |
| 健康・メンタル不調 | ストレス、ハラスメント、相談体制不足 | 心身の不調による離脱 |
内閣府・厚労省「働きやすい・働きがい職場づくり調査」では、メンター制度を導入している中小企業はわずか12.5%にとどまっています。
一方で、多くの企業は目標管理制度や多重評価制度は導入済みであり、制度の運用・浸透不足がギャップの要因となっています。
傾向と分析:国内動向・世代別
業界別・規模別の離職傾向
ポストコロナ時代の変化
リモートワークやハイブリッド勤務の普及に伴い、働き方の選択肢は増えました。その一方で、「仕事と私生活の境界が曖昧」「孤立感が強まった」といった副作用も表面化しています。働き手側としては、働き方における柔軟性や自己裁量を重視する傾向が一層強まりました。
世代別価値観のシフト
価値観は世代によって大きく異なり、それが「離職理由」や「職場満足度」に影響しています。特にZ世代・ミレニアル世代と、バブル・団塊ジュニア世代とでは、仕事に求めるものが大きく異なります。以下は、主な価値観の違いを示した比較表です。
世代別価値観比較表
| 価値観項目 | Z・ミレニアル世代(20〜30代) | バブル・団塊ジュニア世代(40〜60代) |
| 働きがい重視 | ◎ | △ |
| 給与・安定重視 | △ | ◎ |
| 理念・社会貢献との共感 | ◎ | △ |
| 柔軟な働き方志向 | ◎ | △ |
| 長期雇用・終身雇用志向 | △ | ◎ |
| キャリアの自己決定重視 | ◎ | △ |
| 評価の透明性重視 | ◎ | △ |
| 責任感・安定志向 | △ | ◎ |
記号の意味
◎:重視されている | △:あまり重視されていない・個人差が大きい
このように、若年層では「自律性」「意味」「共感」を重視する傾向があり、年長層は「安定性」「組織への忠誠」「責任感」を重んじる傾向があります。企業はこれらの違いを理解し、それぞれに応じたマネジメントや制度設計が求められます。
たとえば、若手にはミッション共感型の評価制度やパーパス経営の導入が効果的であり、中堅以上の世代にはスキル承継や役割の再定義が重要です。組織に多様な世代が共存する現在、これらの世代間ギャップを「活かす」視点が、企業の持続的成長に直結します。
成功事例:離職防止に成功した企業施策
社員満足度を高め、離職率を大幅に改善した企業の多くは、制度を整えるだけでなく、運用と文化まで落とし込む点に共通点があります。
ここでは、業界別に社員満足度向上と離職率低下の両立に成功した事例を紹介します。
【IT・テック業界】柔軟な働き方改革で離職率を半減|サイボウズ株式会社
サイボウズは、「100人いれば100通りの働き方」を掲げ、フルリモート勤務、副業自由化、勤務地選択制など、個人最適型の制度を導入しています。
制度だけでなく、チーム単位での裁量を認める「働き方宣言制度」を設け、社員が自ら働き方を設計できる環境を構築しました。
これらの取り組みにより、離職率は28%から4%台まで改善し、現在では国内外から「心理的安全性の高い組織」として高く評価されています。
出典:サイボウズ株式会社『人的資本データ一覧』(2024年)
出典:Unipos『離職率28%からの脱却|サイボウズ事例インタビュー』(2020年)
【保険・金融業界】“MYパーパス制度”でキャリア納得度を高める|SOMPOひまわり生命保険
SOMPOひまわり生命では、社員一人ひとりが「自分の存在意義(MYパーパス)」を定義し、それに基づいてキャリア選択や異動を行える制度を導入しました。
この仕組みにより、社員のキャリア納得度が向上し、エンゲージメントスコアも前年比で約15%上昇しています。
また、社内での対話機会が増えた結果、「やりがいの実感」と「自律的キャリア形成」の両立が進み、離職率の改善にも寄与しました。
出典:SOMPOホールディングス『統合報告書2024 – 人的資本戦略』
出典:SOMPOひまわり生命『MYパーパス導入に関するニュースリリース』(2022年)
【住宅業界】キャリア自律支援と評価透明化で離職率を低下|積水ハウス株式会社
積水ハウスは、「キャリア自律×公平な評価」を軸にした人的資本経営を推進しています。
全社員を対象に「自己申告型キャリア面談制度」を導入し、キャリア希望と会社方針を可視化。
さらに、360度評価やOKR(目標管理制度)を採用することで、“評価の納得感”と“挑戦意欲”の両立を実現しました。
この結果、社員のモチベーションと定着率が向上し、人的資本開示の先進企業としても注目されています。
出典:積水ハウス株式会社『サステナビリティ価値報告書2024』
出典:SmartHR『スマートHRアジェンダ Vol.2 積水ハウス対談記事』(2023年)
【中小企業】社員満足度の可視化で離職率を30%削減|製造業A社の実例
ある中小製造業では、社員満足度調査と1on1面談制度を組み合わせた“ES強化プロジェクト”を実施。
施策導入から1年で、離職率が30%減少し、社内アンケートでも「会社に信頼を感じる」と答えた社員が60%→85%に上昇しました。
これにより、「話せる職場」「認められる風土」を醸成。人材定着が進み、採用コスト削減にもつながっています。
出典:note『中小企業が離職率30%を削減した理由|藤野徹(組織人事コンサルタント)』(2022年)
社員満足度を高めることによる経営インパクト
社員満足度の向上は、ただ「働きやすい職場」にとどまらず、経営面で多くのプラス波及効果を生みます。以下は、企業が得られる代表的なインパクトと、それを実現するための背景です。
① 離職率の低下/定着率の向上
社員満足度(ES)が上がると、離職意向が下がり、定着率が高まるという実証研究があります。例えば、ESが高い企業ほど離職率・新人定着率ともに有意に良好であることが報告されています
出典:日立総合計画研究所「Employee Satisfaction(従業員満足度)」
② 採用コストの削減
定着率が上がることで、採用からオンボーディング・教育までのコストが減少します。また、社員が口コミやSNSで「働きがいのある職場」と発信すれば、採用時の応募者数・質も高まります。
③ 業績・生産性の向上
満足度の高い社員はモチベーション・没入度が上がり、生産性に好影響を及ぼします。実際に「Employee Satisfaction と企業業績との関連性」を示した研究もあります。
出典:サイエンスダイレクト+1
④ 顧客満足(CS)の改善
社員体験(EX)が良好であれば、顧客接点に立つ社員の振る舞いやサービス品質も向上し、顧客体験(CX)に好影響を与えることが指摘されています。
出典:富士通+1
⑤ 企業ブランド強化・採用競争力向上
“この会社で成長できる”“この会社にいると認められる”と感じる社員が多い企業は、外部からも魅力的なブランドとして認知され、優秀人材の応募が増える傾向があります。
⑥ ESG・CSR観点での評価向上
社員満足度や人材定着率はサステナビリティ報告書などで注目される指標であり、ESG投資やCSR活動の観点からもプラスの影響があります。
ワンポイント:近年では、「EX(Employee Experience)改善 → CX(Customer Experience)改善」という流れが明確になっており、社員満足を高めることが“お客様体験の質”をも引き上げる鍵となっています。
実践的改善策
以下は、社員満足度を高め、離職率を低下させるための具体的改善策と、運用上押さえておきたいポイントです。
① ES調査(社員満足度調査)の高度化
チェックリスト:
② 1on1・対話制度の運用強化
③ 評価制度・キャリア制度の再設計
④ 働き方改革・柔軟制度導入
⑤ 福利厚生・健康支援制度の充実
⑥ メンター制度・傾聴文化醸成
⑦ 改善サイクル運用(PDCA)
健康経営との統合アプローチ
社員満足度向上戦略と「健康経営」を統合することで、相乗効果が得られます。以下の4つのステップで設計・運用すると有効です。
- 理念統合:企業理念×健康支援ポリシーを明文化
社員一人ひとりの「ウェルビーイング(健康で働き続けられる状態)」を企業価値として掲げ、理念の一部に位置づけます。 - 制度設計:メンタルケア制度・フレイル予防プログラム・健康増進体制の構築
例:ストレスチェック強化、定期的な健康運動プログラム、食事・睡眠改善支援。 - 可視化:健康指標・ストレススコアを定期モニタリングし、改善傾向を報告
例:体重・血圧・休職率・ストレススコアを半年毎に集計し部門別分析。 - 認証取得:健康経営優良法人制度などで社外からの評価を得る
認証取得を通じて、対外的な信用力・採用ブランディングが強化されます。
補足:導入企業の調査では「社員満足度と生産性が同時に改善した」という報告もあります。
離職防止ツールとDX化戦略
現代の人材定着戦略では、“見える化”と“即応性”が重要です。デジタルツールを活用して、離職予兆を早期発見・対応できる体制を整えましょう。
ツール例と特徴
HRBrain:タレントマネジメントと社員満足度調査を統合、配置最適化も支援。
Wevox:組織スコアを可視化し、改善アクションまでを支援。
カオナビ:社員の状態・配置・コンディションを管理できるプラットフォーム。
DX導入の成功ポイント
① ツールを目的から設計する:ツール導入が目的にならず、「何を改善したいか」「どんな指標を上げたいか」を明確に。
② データ活用文化を育成する:ツールで得たデータを活用できる人材とルールを整備。
③ 導入前に業務フローを整理し属人化を排除:ツールは属人化を可視化するため、前提として業務の“見える化”が必要。
④ 継続運用支援と改善会議体を設置:導入後に離脱せず、定期的に数値・活用状況・改善案を議論する。
⑤ 文化変革と並行して進める:ツールだけで離職率は下がりません。組織文化・働き方・評価制度も同時に変革することが鍵です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 社員満足度とエンゲージメントの違いは?
→ 満足度は「現在の満足感」、エンゲージメントは「組織への熱意・関与度合い」。
Q2. 離職率の“適正値”とは?
→ 5〜10%程度が低め目安。ただし業界・企業条件によって大きく異なる。
Q3. 調査実施頻度は?
→ 半年〜四半期に 1 回。リアルタイム可視化型導入企業も増加中。
Q4. 中小企業でもできる対策は?
→ メンター制度・1on1導入・働き方改善など、低コストから始められる施策あり。
Q5. 満足度が高くても離職するケースは?
→ はい。転職希望、自己起業、家庭事情など、満足度以外の要因も影響。
10. まとめとアクションプラン
「自社でも離職率改善を始めたい」と思った方は、まずは社内のES調査(社員満足度調査)からスタートしてみましょう。調査の設計や実施に不安がある場合は、外部ツールや支援サービスの活用が効果的です。
今すぐ始める 3 ステップ
- 現状把握:離職率や満足度の実態を“見える化”する
- パイロット施策の実行:1〜2部署で小規模に試験導入
- 効果検証・横展開:成功事例を分析し、全社展開へ
社員の“声”を活かすには、仕組みとツールの両立がカギ
社員の声に耳を傾け、その本音を知り、誠実に応えること──。それこそが、離職を防ぎ、組織を強く、しなやかにする最短ルートです。
ただし、「声を聞く」だけでは不十分です。重要なのは、その声を“データ”として定期的に収集・分析し、現場と経営層が共有できる仕組みを持つこと。
離職防止と定着率改善に、弊社のSaaSが貢献します
弊社が提供する「人材マッチング・育成支援プラットフォーム」は、採用から定着・育成までを一気通貫で支援するソリューションです。
特に以下の機能が、離職リスクの予防や早期対応に効果を発揮します:
- エンゲージメント診断:部署別にやりがいや満足度を可視化
- シンクロ率診断:既存社員との相性をもとに最適な配属を提案
- マッチング率診断:求職者と理想の人材像を科学的に照合
- 面接サポート:ギャップのある特性をもとに再質問ポイントを提示
- 採用サイト連携:応募と同時に自動診断・情報開示が可能
また、今後はeラーニング型のオンボーディング支援やAIによる規定検索機能も展開予定で、採用・育成業務のDXを強力に後押しします。
社員満足度を“数値”として捉え、離職予兆を“可視化”し、改善施策を“自動化”できる──。これが、これからの人事部門に求められる新しい標準です。
まずは、自社に合った1つの機能から試してみませんか?