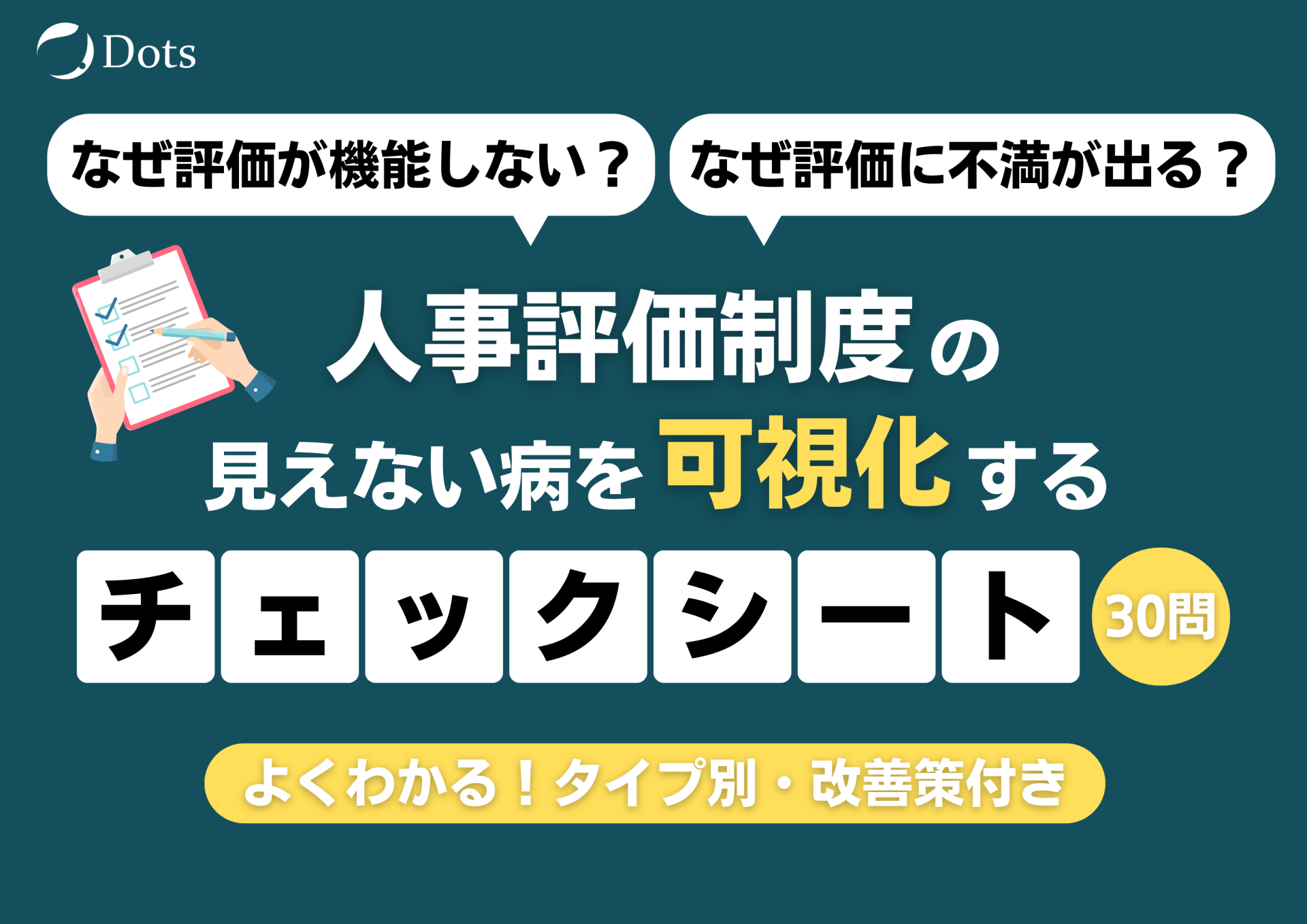若手社員の離職を防ぐ!今すぐ実践できる若手定着施策と成功のポイント
ブログ
2025.11.05

「最近、若手がすぐ辞めてしまう…」と感じていませんか?
企業にとって、若手社員の早期離職は深刻な損失です。採用や育成に投資した時間やコストが無駄になるだけでなく、組織の安定性や知識の継承にも大きな影響を及ぼします。
とくにZ世代を中心とした若手層は、給与や安定よりも「成長実感」や「働きがい」といった内的動機を重視する傾向が強く、従来型のマネジメントや制度では定着させにくくなっています。
そんな中で注目されているのが「若手定着施策」。単に辞めさせないのではなく、「ここで働き続けたい」と自ら思ってもらえる環境づくりこそが企業の競争力を左右する時代です。
本記事では、若手社員の離職防止に直結する具体的な施策やその背景、中小企業でも実行可能な工夫、そして実践を後押しする支援ツールの活用方法まで、わかりやすく解説します。

若手社員の「離職」が企業に与える重大な影響
若手社員の離職は、単なる人数の減少では済みません。企業にとって、直接的・間接的に深刻な影響をもたらす「経営課題」そのものです。
若手離職による採用・育成コストの損失
1人の若手社員が辞めるだけで、広告費、人材紹介料、面接対応、研修・OJTなど、多大なコストが水泡に帰します。中小企業の場合、その影響はさらに顕著で、再採用・再教育にかかる人的リソースの逼迫は業務全体の生産性をも下げかねません。
厚生労働省の調査(2022年度)でも、新卒就職者の約3人に1人(32.8%)が3年以内に離職しているという現実が明らかになっています。
Z世代に見られる価値観と転職スタンスの変化
Z世代といわれる90年代後半〜2000年代前半生まれの世代は、物心ついたときからインターネットとスマホに親しんできました。SNSを通じて価値観を共有し、自分らしさを重視する傾向が強く、「働き方」や「職場文化」の違和感に敏感です。
また、転職サービスや口コミサイトの普及により、職場の“リアル”を比較しながら行動する習慣が定着。違和感を感じれば即座に離職を選ぶフットワークの軽さも特徴です。
若手定着施策が今、企業に必要な理由とは
採用・教育投資を守るための施策設計
採用コストの回収には少なくとも3年程度かかるとされます。にもかかわらず、早期離職が続けばその投資は回収不可能。つまり「採用して終わり」ではなく、「定着して初めて成果」と言えるのです。
Z世代の価値観とエンゲージメントの関係
Z世代の多くは、給与額よりも「どう成長できるか」「どんな人と働くか」といった“中身”を重視しています。企業はこの価値観に寄り添い、働きがいや挑戦機会を提供できる体制を整えることが急務です。
企業競争力と組織ブランド強化にも直結
社員が定着することで、ノウハウや業務効率が蓄積され、企業文化も安定していきます。それが結果として顧客満足度の向上、サービス品質の向上につながり、企業ブランドそのものの競争力を高める要因となります。
参考: AI経営総合研究所+1
参考:kyozon+1
参考: AI経営総合研究所
若手社員が定着しない原因はこの5つ
採用ミスマッチによるギャップ
最も多い原因のひとつが「採用段階でのミスマッチ」。募集情報にはポジティブな要素だけが記載されがちで、業務内容や評価基準、職場文化などの“現実”が伝わらないまま入社すると、「想像と違う」と早期離職につながります。
とくにZ世代は情報感度が高く、入社前の期待と現場のギャップに敏感に反応します。企業は“ありのまま”を伝える工夫が求められます。
成長実感とキャリア支援の不足
若手にとって「この会社で何が身につくのか」「どんなキャリアが描けるのか」は重要な判断軸。日々の仕事がルーティンで終わってしまい、自分の成長を感じられない環境では、長く働きたいとは思えません。
また、キャリア面談やスキルアップ支援など、将来に向けた“導き”が見えないことも、モチベーション低下の一因です。
評価・処遇制度の不透明さ
「何をすれば評価されるのか分からない」「評価されている実感がない」。こうした不透明さは、若手の働く意欲を確実に削ぎます。
納得感のある評価制度には、明確な基準と定期的なフィードバックが不可欠です。
働き方の多様化への未対応
リモート勤務、副業OK、柔軟な勤務時間など、働き方へのニーズは多様化しています。Z世代は「働く場所・時間」よりも、「働き方の自由度」を重視する傾向があり、それに対応できない企業は敬遠されがちです。
制度だけでなく、実際に活用される“文化”として根づかせることが鍵です。
人間関係・職場文化の影響
若手社員は職場の人間関係や雰囲気を重視する傾向があります。上司との信頼関係が築けなかったり、孤立感を抱いたりすると、「続けたい」とは思えなくなります。
チームや職場全体が“相談しやすい雰囲気”を持っているかどうかも、定着の成否を分ける要素です。
- 参考:note(ノート)+1
- 参考:AI経営総合研究所
【実践例つき】若手社員の定着を高める6つの施策+α
ここでは、若手社員が安心して働き続けられる職場づくりに役立つ、実践的な施策をご紹介します。各施策には「目的」「具体例」「中小企業向けの工夫」も付け加え、実行しやすさを重視しています。
① 採用段階でのミスマッチ防止
目的
入社後のギャップを減らし、早期離職を防ぐ。
具体例
仕事内容・評価基準・職場の雰囲気を事前に伝える。たとえば、職場体験、社員インタビュー、リアルな現場動画の活用など。
中小企業向け工夫
「1日体験」や「現場座談会」を簡易的に実施したり、SNSで若手社員の声を発信したりすることで、コストを抑えつつリアルな情報提供が可能です。
② 定期的なコミュニケーション機会の設定
目的:若手の孤立を防ぎ、不安や疑問を早期にキャッチする。
具体例
1on1面談、メンター制度、チーム横断のミーティング、オンライン雑談会など。
中小企業向け工夫
月1回の上司面談や「先輩と若手のペア制度」など、少ない工数で継続できる方法を選ぶとよいでしょう。Slackなど社内SNSを活用した雑談チャネルも効果的です。
③ 成長機会とキャリア支援の提供
目的
若手自身に「成長できる」という実感を持ってもらう。
具体例
スキルアップ研修、外部セミナー支援、社内ジョブローテーション、資格取得支援など。
中小企業向け工夫
「社内勉強会」「OJT+メンター制」「地元の研修機関との提携」など、小規模でも始めやすい取り組みがあります。
④ 公正かつ透明な評価制度の構築
目的
「何が評価されるか」が明確で、納得感ある制度づくり。
具体例
評価項目の見える化、目標の事前設定、360度評価、定期的なフィードバック面談。
中小企業向け工夫
評価基準を簡易に設定し、社員にも公開。半年ごとの面談を設定するなど、運用面での工夫も有効です。
⑤ 柔軟な働き方を可能にする制度の整備
目的
多様な働き方ニーズに対応し、長く働ける環境を提供する。
具体例
リモートワーク、時差出勤、副業解禁、休暇取得支援、メンタルヘルス対応制度など。
中小企業向け工夫
「月1回リモート可」や「時短勤務の導入」など、小さく始めて段階的に広げていく方法がおすすめです。制度の利用実績を見える化して社内に浸透させましょう。
参考: エデンレッド+1
⑥ データ分析による定着施策の継続改善を実施する
目的
感覚ではなく、データに基づく継続的な改善を行う。
具体例
離職率の推移分析、エンゲージメント調査、退職理由のヒアリング、部署別の比較分析など。
中小企業向け工夫
Excelやスプレッドシートでの簡易集計から始め、アンケートや面談記録を活用して、離職要因を“見える化”します。
参考: AI経営総合研究所+1
+α:若手向けオンボーディング・初期フォロー
目的
入社初期の不安を取り除き、職場に早く馴染ませる。
具体例
メンター制度、3ヶ月間の集中フォロー、若手同士の横のつながりづくり(ランチ会・同期会など)
中小企業向け工夫
先輩社員をバディにして非業務的なフォローも実施する、定期的な「何でも聞いていい雑談会」など、リソースを使わずにできる方法が多数あります。
若手が定着しない企業に共通する落とし穴とその対策
若手定着施策に力を入れていても、なかなか成果が出ない企業には共通した「落とし穴」があります。ここでは、よくある4つの落とし穴とその対策を紹介します。
入社前後のギャップ
課題
入社前に提示された仕事内容や社風と、実際の業務・職場環境にズレがあると、若手は「裏切られた」と感じ早期離職に直結します。
対策
リアルな職場紹介や社員の声を採用段階で提示し、可能なら職場体験を実施。動画やSNSを活用して、日常の雰囲気を伝えるのも効果的です。
キャリア成長の見通しがない
課題
「このままでいいのか?」と将来に不安を感じると、成長意欲の高い若手ほど離職を選びます。
対策
スキルアップのための支援制度、キャリアパスの例示、定期的なキャリア面談を設けるなど、「成長実感」を伴う取り組みが必要です。
評価・処遇の不透明さ
課題
「どうすれば評価されるのか分からない」「自分の頑張りが反映されていない」という状態は、不信感やモチベーション低下を招きます。
対策
評価基準の見える化と説明機会の確保、面談を通じた納得感のある運用が重要です。360度評価などの導入も有効です。
多様化する働き方への未対応
課題
「場所・時間に縛られる働き方」は今の若手にとって魅力が薄れています。制度があっても利用しづらい職場文化も問題です。
対策
リモートや時短勤務、副業の解禁など、柔軟な制度を段階的に導入し、トップや管理職が率先して利用することで“制度が使いやすい雰囲気”をつくりましょう。
これらの課題は複合的に重なって若手の離職を引き起こすことが多いため、優先順位をつけながら着実に改善していく姿勢が求められます。
参考: note(ノート)
中小企業が取り組むべき若手定着の工夫
大手企業と違い、リソースが限られる中小企業でも、創意工夫によって若手社員の定着率を高めることは可能です。ここでは、現実的かつ効果的な対策を紹介します。
非金銭的価値を高める
給与や福利厚生で勝負が難しい中小企業こそ、「働きやすさ」「やりがい」「人間関係」といった非金銭的な価値の強化が重要です。
実践例:
地域性・文化を魅力に変える
地方企業や地域密着型の組織では、都市部にはない「地域貢献」「地元密着でのキャリア構築」といった独自の魅力があります。
実践例:
施策に優先順位をつけて段階的に実行
すべてを一度に整備しようとすると、途中で頓挫しがちです。実行しやすい施策から始め、少しずつ浸透させる方が成功確率は高まります。
おすすめの優先ステップ:
- 1on1面談の定着
- オンボーディング施策の充実
- キャリアパスや評価基準の明文化
- 柔軟な働き方制度の導入
制度を“文化”として浸透させる
制度があっても「使われない」ことはよくあります。特に中小企業では、「制度の活用=恥ずかしい、遠慮が必要」という空気を払拭する必要があります。
実践例:
- 管理職が自ら制度を活用する
- 成功事例を社内で共有する
- 社内報や朝礼などで制度利用の推進を図る
簡易でも“見える化”による改善を続ける
専門的なHRツールがなくても、手元の情報で十分にデータ活用は可能です。まずは「把握すること」から始めましょう。
簡単な分析ポイント:
小さな工夫を積み重ね、現場で実感できる施策を少しずつ積み上げていくことが、定着率改善の王道です。
参考:AI経営総合研究所+1
参考: AI経営総合研究所
実践に向けたチェックリスト&KPI設計
若手定着施策を形だけの取り組みに終わらせないためには、「継続的な確認」と「成果の見える化」が欠かせません。ここでは、自社の現状を確認するためのチェックリストと、効果測定に使えるKPI例を紹介します。
チェックリスト:自社の現状把握に使える9項目
以下の質問に「YES」と自信を持って答えられるかを、定期的に振り返ることが重要です。
KPI(重要指標)例:施策の効果を可視化するために
施策の成果を「数値」で追うことは、改善を加速させるための鍵です。以下のKPIは、実施状況や満足度の把握に役立ちます。
KPIは「定着率」だけを追うのではなく、その背景にあるプロセスや感情面にも目を向けることが重要です。数値と実感、両方を捉えた分析で、施策の質を高めていきましょう。
まとめ
若手定着施策は、単なる「早期離職を防ぐための手段」ではありません。
それは、企業の未来を支える人材をどう育て、どう活かし、どう共に成長していくかという、組織文化そのものを問い直す機会です。
Z世代を中心とした若手社員は、これまでの常識とは異なる価値観を持ち、働き方やキャリア観に強い個性を持っています。だからこそ、企業は柔軟かつ戦略的に、若手が「働き続けたい」と思える環境を整えていく必要があります。
定着支援には、仕組みと可視化が不可欠
採用・教育・評価・働き方のどこか一つではなく、これらを“つないで見える化”し、継続的に改善していくことが不可欠です。
その実現をサポートするのが、弊社が開発した 「人材マッチング・育成支援プラットフォーム」 です。
弊社システムのご紹介:採用から定着・育成まで、これ一つで完結
パーソナリティ診断
求職者の価値観や性格特性を明らかにし、企業と求職者の相性を事前に可視化します。
マッチング率&シンクロ率分析
求職者と自社の理想人材像や既存社員との親和性を数値で可視化し、配属やチーム設計に活用できます。
面接サポート機能
ギャップが生まれやすいポイントを抽出し、再質問のヒントを提示。ミスマッチ防止に貢献します。
エンゲージメント診断
既存社員の満足度・やりがい・ハラスメント懸念まで含めて、組織の健康状態を可視化&改善。
組織診断・定期サーベイ機能
部署ごとの傾向分析や経年変化の可視化により、点ではなく“面”での定着支援が可能に。
今後の拡張機能(開発中)
eラーニング/独自研修コンテンツ/AI制度検索機能/採用サイト連携など、育成・情報開示も支援。
導入をご検討中の企業様へ
若手の離職に悩む企業様こそ、「入社前から、定着の土台を整える」このシステムの効果を実感いただけます。
「採用の質を高めたい」
「入社後の配属ミスを防ぎたい」
「定着率を継続的に改善したい」
そんなご担当者様は、ぜひ一度、以下のリンクよりシステム詳細をご覧ください。
企業と人材の“見えないギャップ”を可視化し、成長をともにできる仕組みを提供します。