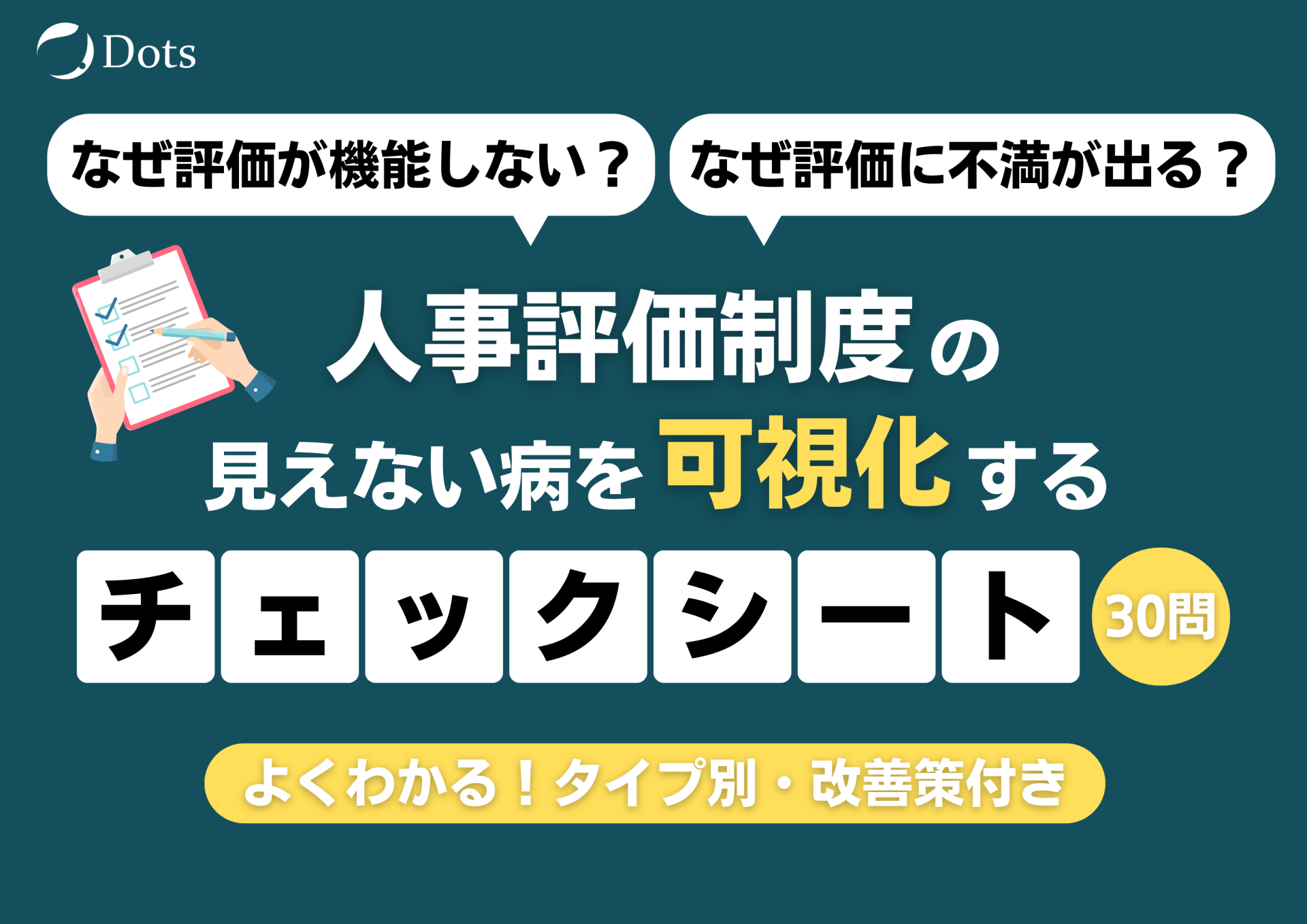【比較表あり】ジョブ型雇用 vs メンバーシップ型雇用|2024年最新の違いと企業の選択肢
ブログ
2025.06.19
公開日:2021年2月28日
更新日:2025年6月19日


ジョブ型雇用 vs メンバーシップ型雇用:今、企業が直面する重要な選択とは?
「この人材、本当にうちに合っているのだろうか?」採用の現場でそんな疑問が浮かぶことはありませんか?働き方改革、リモートワークの定着、そして人口減少という社会的背景から、日本の雇用システムは大きな転換点を迎えています。その中で注目を集めているのが、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」という2つの異なる雇用モデルです。
この記事では、両者の違い、メリット・デメリット、導入の障壁、国内外の導入事例、そして今後の人事戦略における最適な選択肢について、図表や事例を交えてわかりやすく解説していきます。
ジョブ型雇用とは?職務を軸とした雇用システムの特徴
- 職務内容が明確に定義されている
- 専門スキルや成果で評価される
- 市場価値に基づく報酬体系
- 中途採用・専門職採用が中心
- 職務に応じた限定的な業務範囲
ジョブ型雇用では、従業員は自分の専門分野に特化して働き、その領域での成果や貢献度によって評価されます。このため、スペシャリストとしてのキャリア形成が可能になります。
メンバーシップ型雇用とは?長年日本を支えた雇用モデル
- 職務内容は曖昧だが幅広い
- 年功序列や勤続年数で評価
- 配置転換・転勤が頻繁
- 新卒一括採用と親和性が高い
- 企業への帰属意識を重視
日本の高度経済成長期を支えたこのモデルは、長期雇用を前提とした安定志向に根差しています。従業員はゼネラリストとして様々な部署を経験し、企業全体を理解した人材として育成されます。
ジョブ型とメンバーシップ型の違いとは?一覧表で徹底比較
| 特徴 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 明確・限定的 | 広く曖昧 |
| 評価基準 | スキル・成果 | 勤続年数・勤務態度 |
| 報酬体系 | 市場価値・成果型 | 年功序列型 |
| 異動の頻度 | 少ない(職務基準) | 多い(柔軟配置) |
| 採用方式 | 中途・職務ベース | 新卒・ポテンシャル採用 |
| キャリア形成 | スペシャリスト志向 | ゼネラリスト志向 |
| 雇用の安定性 | 職務継続が前提 | 長期雇用が前提 |
Point:企業文化や人材戦略により、どちらが適しているかは異なります。
ジョブ型・メンバーシップ型のメリット・デメリット比較
ジョブ型雇用のメリット・デメリット
メリット
- 専門性向上とキャリアパスの明確化
- 成果重視の公正な評価システム
- 即戦力人材の効率的な採用
デメリット
- 組織の柔軟性低下と業務範囲の制約
- 専門人材確保の難しさと採用コスト増加
メンバーシップ型雇用のメリット・デメリット
メリット
- 組織の一体感と柔軟な人材配置
- 長期的視点での人材育成とゼネラリスト輩出
デメリット
- 専門性の不足とグローバル競争力の課題
- 年功序列による評価の不透明性
採用と育成:ゼネラリスト文化とジョブ型のギャップ
従来のメンバーシップ型との違い
- 日本の新卒一括採用
- ポテンシャル重視での採用
- OJTやジョブローテーションによるゼネラリスト育成
- 組織適応力や忠誠心を重視
ジョブ型が求める人材
- 即戦力となる専門スキル
- 明確な職務要件への適合
- 成果重視の評価システム
導入に向けた転換策
- ジョブディスクリプションの整備
- 職務内容と必要スキルの明文化
- 成果指標の明確な設定
- 採用プロセスの見直し
- スキルベース面接の導入
- 実務経験重視の選考基準
- 専門性重視の育成体系
- 分野特化型研修プログラム
- 継続的なスキル開発支援
2024年最新|ジョブ型雇用の国内導入事例一覧
NTTグループ
- 2023年4月より、18の専門分野に基づく「グレード基準」を導入
- 専門性に応じた報酬体系と昇給・昇格の仕組みを構築
- キャリア開発支援を強化
(出典:NTTグループ公式ニュースリリース「専門性を軸とした人事給与制度への見直しについて」)
富士通
- 2026年度新卒採用より「ジョブ型人材マネジメント」を拡大
- 有償インターンシップの拡充と採用プロセス見直し
(出典:富士通公式プレスリリース「新卒採用への『ジョブ型人材マネジメント』の拡大について」)
資生堂
- 2020年から全社員向けキャリアワークショップを実施
- 部署別ジョブディスクリプションを作成
- eラーニングによる継続的スキル開発支援
(出典:資生堂企業情報「人材育成と公正な評価」)
海外企業のジョブ型雇用の参考事例
- 詳細なジョブディスクリプションの設定
- OKRなどの成果指標に基づく評価システム
- スキル可視化システムの導入と継続的開発プログラム
人事DXとジョブ型雇用:デジタル化がもたらす変革
重要な要素
- スキルの定量評価と可視化
- パーソナリティ分析とマッチング
- 職務要件との適合度測定
HRテックの活用領域
- 採用管理システム(ATS)
- 人材管理システム(HCM)
- パフォーマンス管理ツール
- スキル管理プラットフォーム
(出典:経済産業省「未来人材ビジョン」)
ジョブ型雇用導入のステップ:段階的アプローチが成功の鍵
混合型(ハイブリッド型)の導入戦略
- IT・DX人材や研究開発職:ジョブ型導入
- 総合職・事務職:メンバーシップ型継続
- 管理職:混合型アプローチ
段階的な制度設計
- 基盤整備:ジョブディスクリプションと評価基準の明確化
- 制度運用:パイロット部署での試行と管理職研修
- 本格展開:全社導入と継続的改善
導入成功のポイント
- 経営層のコミット:変革意志とリソース確保
- 従業員の理解促進:背景説明と継続的コミュニケーション
- 柔軟な制度設計:文化に応じたカスタマイズと見直し
ジョブ型雇用導入時の注意点
労働法制への対応
- 職務変更時の同意取得
- 解雇規制への適切な対応
- 労働条件の明示義務遵守
従業員のモチベーション管理
- 透明性の高い評価制度の構築
- キャリア開発支援の充実
- 定期的な面談とフィードバック実施
今後の展望:2025年以降のトレンド
- AIとジョブ型雇用の融合
自動化と高度化が進み、継続的なスキルアップデートがより重要に。 - グローバル人材獲得競争
明確な職務定義と競争力ある報酬体系が鍵。
まとめ|未来に向けた柔軟で実践的な雇用戦略を
これからの時代、画一的な雇用モデルでは変化に対応できません。個々の職務に合わせた柔軟な働き方、明確な評価と報酬設計が、持続的な成長の鍵となります。
重要なポイント
- ジョブ型雇用は万能ではなく、企業の特性に応じた導入が重要
- 段階的な導入とハイブリッド型アプローチが現実的
- 人事DXの活用により、データに基づいた人事運営を実現
- 従業員の理解と協力が成功の前提条件
人事制度の見直しに悩む企業様へ|Dotsがジョブ型雇用導入を支援します
- 「ジョブ型を導入したいが、どこから手を付けてよいか分からない」
- 「ジョブディスクリプションの整備に手が回らない」
- 「スキルに基づく評価制度が定まらず、属人化している」
- 「採用した人材が職務にフィットしていない」
- 「人事異動や配置が感覚頼りでミスマッチが起きている」
Dotsのシステムで解決できること:
- データドリブンな人事運営の実現
- マッチング率の数値化により、採用の精度を可視化
- パーソナリティ診断と職務要件の照合で、最適な配属を支援
- スキル・行動傾向の分析を通じて、評価の納得性を向上
- エンゲージメント指標の追跡により、離職防止や組織改善にも活用
「制度の移行に悩む」そのタイミングこそが、変革のチャンスです。Dotsは、現場の運用まで見据えた実践的なジョブ型導入支援をお約束します。

おすすめ資料:人事評価制度【事例集】
近年、雇用モデルの違いは、人事評価制度の設計にも大きく影響します。
ジョブ型・メンバーシップ型のどちらを採用するかによって、評価項目・昇格基準・処遇連動の考え方も変わるため、制度全体を俯瞰する視点が不可欠です。
実際の中小企業で運用されている評価制度を、評価項目・昇降格基準・報酬ロジックまで詳しくまとめた事例集をご用意しています。