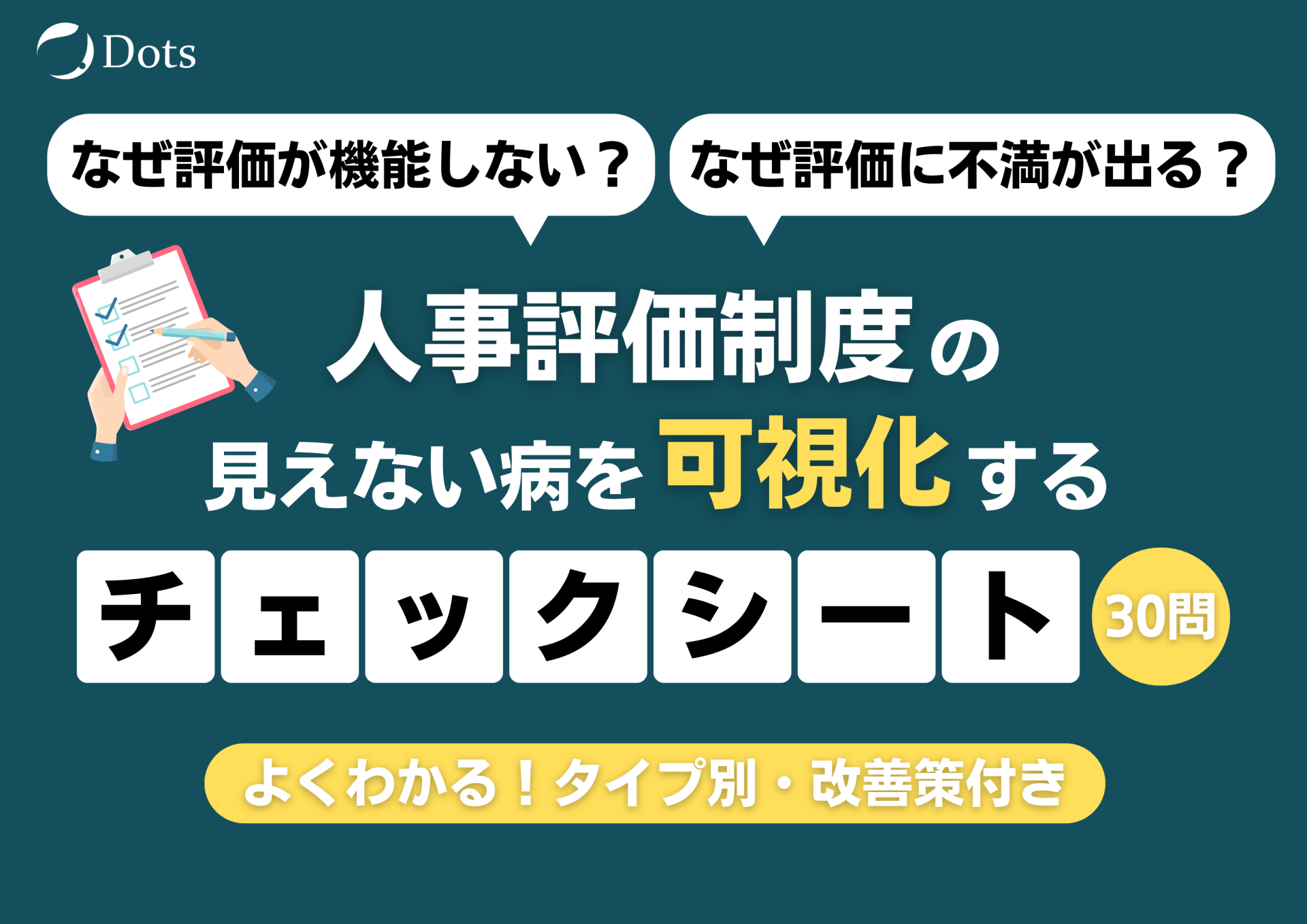【完全ガイド】人事制度の見直しで失敗しないための10ステップ|最新トレンドと実践ポイントを徹底解説
ブログ
2025.09.10

はじめに
現代の企業経営において、人事制度の見直しは避けて通れない重要なテーマです。テレワークの普及、雇用形態の多様化、デジタル技術の進化により、従来の制度では人材の定着や生産性の向上が困難になっています。たとえば、若手社員が現行の昇格ルールに納得できず、離職につながるケースも少なくありません。制度改定を誤れば、社員の不満や組織の混乱を招くリスクもあるため、戦略的かつ慎重な取り組みが必要です。
本記事は、単なる制度の理論解説にとどまらず、 実際の制度導入プロジェクトで蓄積された“現場視点”と“定量・定性の分析手法”をもとに、10ステップのフレームで実践的に構成しています。 よくある理論先行型ではなく、経営層・人事・現場の三者のバランスに着目したアプローチは、制度が「使える」形で定着する鍵となります。

人事制度見直しの必要性と背景
経営環境が激変する現代では、持続的な企業成長を実現するためにも人事制度の柔軟な見直しが求められています。特に以下の背景が挙げられます。
さらに、Z世代の台頭や中高年層の戦力化という観点も加わり、個別最適な処遇とキャリア支援の両立が企業に求められるようになっています。これまでの制度が暗黙の了解のもとに運用されてきたのに対し、これからの制度は“説明責任”と“可視化”が前提となるのです。
人事制度の構成要素と見直しの基本方針
人事制度は大きく分けて、以下の三本柱で構成されています。
- 等級制度:組織内での序列を定義する
- 評価制度:人材を評価する基準と手法を決定する
- 報酬制度(給与・賞与):評価に基づき報酬を決定する
また、勤務時間、福利厚生、退職金制度なども関連要素として連動します。これらの制度が一貫性を持って設計されていなければ、社員の不信感や誤解を招く原因となります。
見直しにあたっては、以下の原則が基本となります。
近年は人的資本経営の観点から、制度設計の背後にある「人材ポートフォリオ」や「企業文化」との接続も強く意識されています。制度を構造的に組み立て直すだけでなく、社員の納得と共感を得る“語り方”にも注力する必要があります。
人事制度見直しのステップと具体的ポイント【10ステップ】
以下に示す10ステップは、順を追って取り組むことで制度の整合性と実効性を高める構成となっています。それぞれのステップで何を意識し、どう進めるかが、制度の成果を左右します。
STEP1:現状把握(定量・定性分析)
まず、見直しの出発点は現状の把握です。人件費構造、等級ごとの平均年収、年齢・職種別の人員構成など、数値データ(定量)を集めて傾向を読み解きます。同時に、社員の意識調査や面談、経営層ヒアリングなどを通じて組織風土や満足度(定性)の情報を得ます。課題を「見える化」することで、制度見直しの優先順位と方向性が明確になります。
たとえば、社員の価値観や職場文化との相性(カルチャーフィット)を意識したアプローチにより、若手の早期離職を防いだ成功事例もあります。詳しくは、こちらの記事で紹介しています。

STEP2:経営方針と連動した目的の明確化
制度は単独で存在するものではなく、経営戦略や人材戦略と直結しているべきです。たとえば「若手の定着を促進したい」「新規事業に対応できる柔軟な人材配置を実現したい」といった、制度設計の目的を明確に定義します。目的が曖昧なまま進めると、制度は形骸化し、運用に無理が生じます。
STEP3:プロジェクト体制の構築とスケジュール設定
人事制度改革には部門横断的な合意形成が必要なため、人事部門だけでなく各部門のキーパーソンを巻き込む体制が必須です。制度設計における実務と意思決定の役割分担を明確にし、定期的な会議やマイルストーンを設定することで、検討プロセスに一貫性とスピードが生まれます。
STEP4:等級制度の見直し
等級制度は、社員の職責や成長段階を明確にし、評価・給与の根幹となる要素です。職能・職務・役割といった等級の枠組みに加えて、キャリアパスの選択肢(専門職・管理職のダブルトラックなど)を用意することで、社員の納得感が高まります。また、等級ごとに求められるスキルや成果を明示した「等級基準書」の整備も重要です。
STEP5:評価制度の設計
評価制度は「何を」「どう」評価するかを明確にするものです。評価対象としては成果、行動、能力、知識などがあり、手法には目標管理(MBO)、360度評価、上司評価、自己評価があります。重要なのは、制度の透明性と納得性を確保することです。職種別に評価項目を変える、評価者教育を徹底する、評価フィードバックの質を高めるといった工夫が求められます。
評価基準の設計方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。

STEP6:給与制度の再設計
給与制度は等級制度・評価制度と連動して設計される必要があります。基本給の構成要素(年齢給・職能給・役割給・成果給など)をどう組み合わせるか、また同一等級内の昇給余地や評価による変動幅をどう設計するかが重要です。近年は、**評価に基づく昇給差を設けながら、年功的な昇給も一部残す「ハイブリッド型」**を採用する企業が増えています。
STEP7:賞与制度の再構築
賞与制度は、社員の成果・貢献に対して柔軟に報いる仕組みです。給与連動型とポイント型のどちらを採用するかは、業績変動リスクや社員の納得性をどう捉えるかによります。部門別業績やチーム成果も加味する場合、評価基準の一貫性と明確な説明責任が求められます。支給ルールのシンプルさと説明可能性のバランスが肝心です。
STEP8:社内説明と制度の理解促進
制度は「設計する」だけでなく、「浸透させる」ことが必要です。全社説明会、部門別ブリーフィング、FAQの整備、イントラネットでの制度公開など、多面的なコミュニケーション戦略が求められます。経営トップのメッセージや部門長の理解度によって、制度の受け止められ方は大きく変わります。
STEP9:試行運用と改善
全社導入前にパイロット運用を実施することで、評価基準のあいまいさや実務運用上の課題を事前に洗い出すことができます。試行期間中に社員からフィードバックを集め、プロジェクト内で検証・修正しながら精度を高めるサイクルを確立します。これは導入時の混乱を抑えるうえで非常に有効です。
STEP10:本格導入と継続的見直し
制度は導入して終わりではなく、運用後の効果検証と改善が不可欠です。評価と処遇の結果が社員にどう受け止められているか、業績や離職率に変化があるかを定期的にチェックします。KPIの設定や年1回の制度レビュー会議などを通じて、継続的なアップデート体制を築くことが、制度の長寿命化と信頼性向上につながります。
まとめと分析
本記事で取り上げた10のステップは、どれも単独で機能するものではなく、相互に連動しながら全体としての整合性を形成する要素です。たとえば、等級制度と評価制度が矛盾している場合、社員は評価結果に納得できず、モチベーション低下を招きます。また、制度設計が経営戦略と乖離していると、制度が形だけのものとなり、実効性を持ちません。
成功している企業の多くは、経営戦略に基づいた明確な人材像を描き、その理想像を実現する手段として制度設計を行っています。透明性の高い評価制度、納得感のある処遇、そして柔軟に対応できる見直し体制が、人事制度の成否を左右します。
特に中堅・中小企業においては、「人事制度をゼロから作り直す」のではなく、「今ある制度をどこからどう変えるべきか」を現実的に捉えることがポイントです。小さな改善を積み重ね、継続的に運用・修正していく体制が求められます。
要点整理(3つの視点)
- 制度設計は「人材戦略の明文化」と「評価・処遇の実行力」が鍵。
- 成果を上げている企業は、柔軟かつ透明性の高い運用体制を持つ。
- 完璧を目指すのではなく、実践と改善を繰り返すことが成功の近道。

おわりに
人事制度の見直しは、単なるルールの再設計ではなく、経営戦略を実現するための仕組みの再構築です。その本質は、「人をどう活かすか」という問いに対する組織としての答えを示すことにあります。
制度を整えるだけでは不十分です。経営トップのリーダーシップ、現場との対話、運用後のフィードバックループなど、制度を根付かせるための取り組みが欠かせません。
また、変化の激しい時代においては、制度も「生き物」として捉えることが必要です。市場の変化や人材像の進化に合わせて、人事制度を柔軟にアップデートし続ける姿勢こそが、企業の競争力に直結します。
制度は一度で完成するものではなく、変化する経営環境にあわせて磨き続けるものです。自社の成長段階に応じて適切な見直しを行い、「人と組織の力」を最大化する人事制度を構築していきましょう。
参考リンク一覧:
おすすめ資料:人事評価制度【事例集】
人事評価制度について調べている方に、こちらの資料もおすすめです。
実在する中小企業の評価制度をもとに、評価項目・昇降格基準・報酬連動の考え方までを、実際の運用内容をもとに詳しく整理した事例集です。
「そのまま自社に落とし込める」具体例を見たい方は、ぜひ参考にしてみてください。