最低賃金上昇で深まる課題―人件費と生産性のギャップが企業を揺さぶる
ブログ
2025.08.25
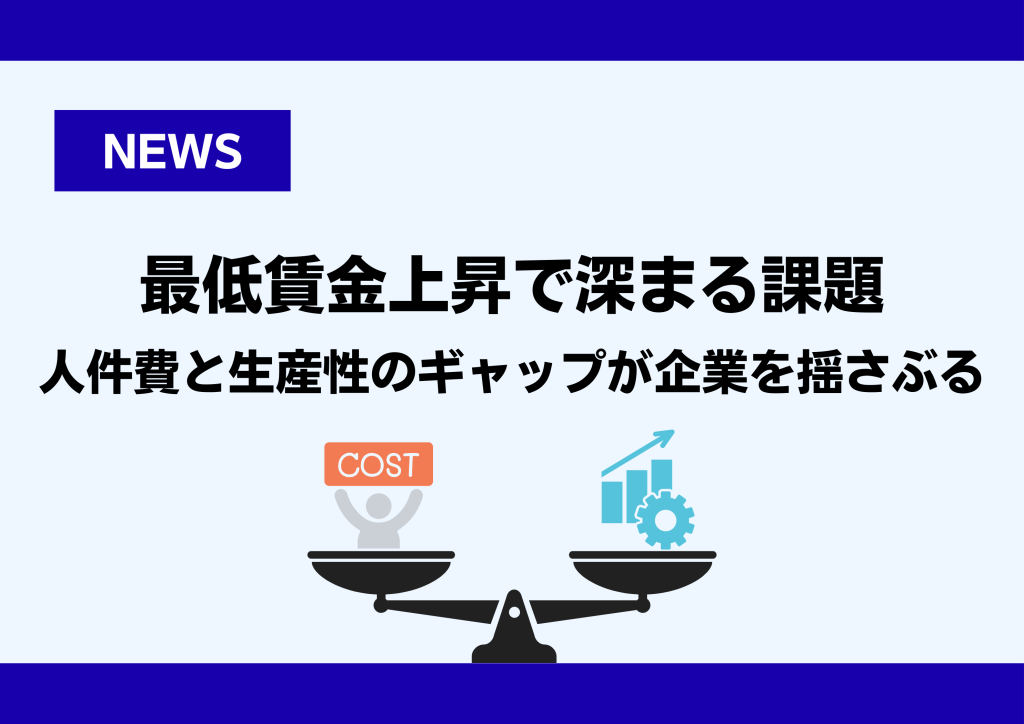
最低賃金の引き上げが続く背景
2025年度も、国が示す目安を上回るかたちで最低賃金の引き上げが各地で予定されています。狙いは、隣県へ人材が流れるのを防ぎ、地域間の所得格差を縮めることです。最低賃金に近い水準で働く人は全国で約660万人にのぼり、多くが中小・零細企業で働いています。働く人の生活を守るうえで引き上げは重要ですが、同時に企業側には重い負担となる可能性があります。
東京と地方で広がる「生産性の差」
内閣府の統計によると、2022年度の就業者1人あたりの生産性(名目額)は、東京都が1225万円と突出しています。一方で最も低い沖縄県は608万円。その差は2倍に達し、東京以外の39道府県の平均は839万円で、東京の約3分の2にとどまります。
この差の背景には産業構造の違いがあります。東京では金融や不動産、情報通信といった高付加価値のサービス業が全体の44.6%を占めます。これに対して地方は26.0%にとどまり、その差は年々広がっています。大阪や福岡など一部の都市は例外的に高い水準ですが、多くの地域では生産性の低さが課題となっています。
賃金引き上げがもたらすリスク
生産性が伸びないまま最低賃金だけが上がると、企業は人件費の増加に直面します。経営の実態に合わない賃金負担を強いられれば、事業縮小や廃業につながるおそれがあります。さらに、人件費の増加を価格に転嫁すれば物価上昇を招き、消費を冷やすリスクもあります。
日本総合研究所の専門家は「最低賃金は、その地域の生産性に合わせて決めることが大切だ。格差をなくすには、地方の生産性を高めることが本筋だ」と指摘しています。
政府も、飲食業や宿泊業など人手不足が特に深刻な12業種を対象に、官民あわせて60兆円規模の投資を進める計画です。ただし、中小企業の現場に本当に役立つ形で実行できるかどうかが課題になっています。
企業に求められる視点
最低賃金の引き上げは避けられない流れです。しかし、地方と都市部の生産性の差はすぐに埋まるものではありません。こうした状況のなかで、企業に求められるのは「賃金以外の部分で人材を確保し、定着させる工夫」です。給与の水準だけでなく、働きやすさややりがいといった要素を高めることが、これからますます重要になっていきます。
人材マネジメントで乗り越える
最低賃金の上昇は避けられませんが、企業が取り組める工夫もあります。その一つが「人材マネジメントの強化」です。人件費の負担が増えても、「人と組織の相性を高める」「社員のやる気を維持する」といった取り組みを積み重ねることで、結果的に生産性を引き上げ、持続的な成長へとつなげることができます。
たとえば――
こうした仕組みを取り入れることで、人件費の負担が増える中でも「人と組織の相性」や「社員のやる気」を高められ、結果的に生産性向上や人材の定着につなげることができます。
もし「自社でも取り入れてみたい」と感じられた方は、まずはお気軽にご相談ください。

出典:日本経済新聞(2025年8月20日)「地方の最低賃金上昇に追いつかぬ生産性 東京の3分の2、引き上げ急務」


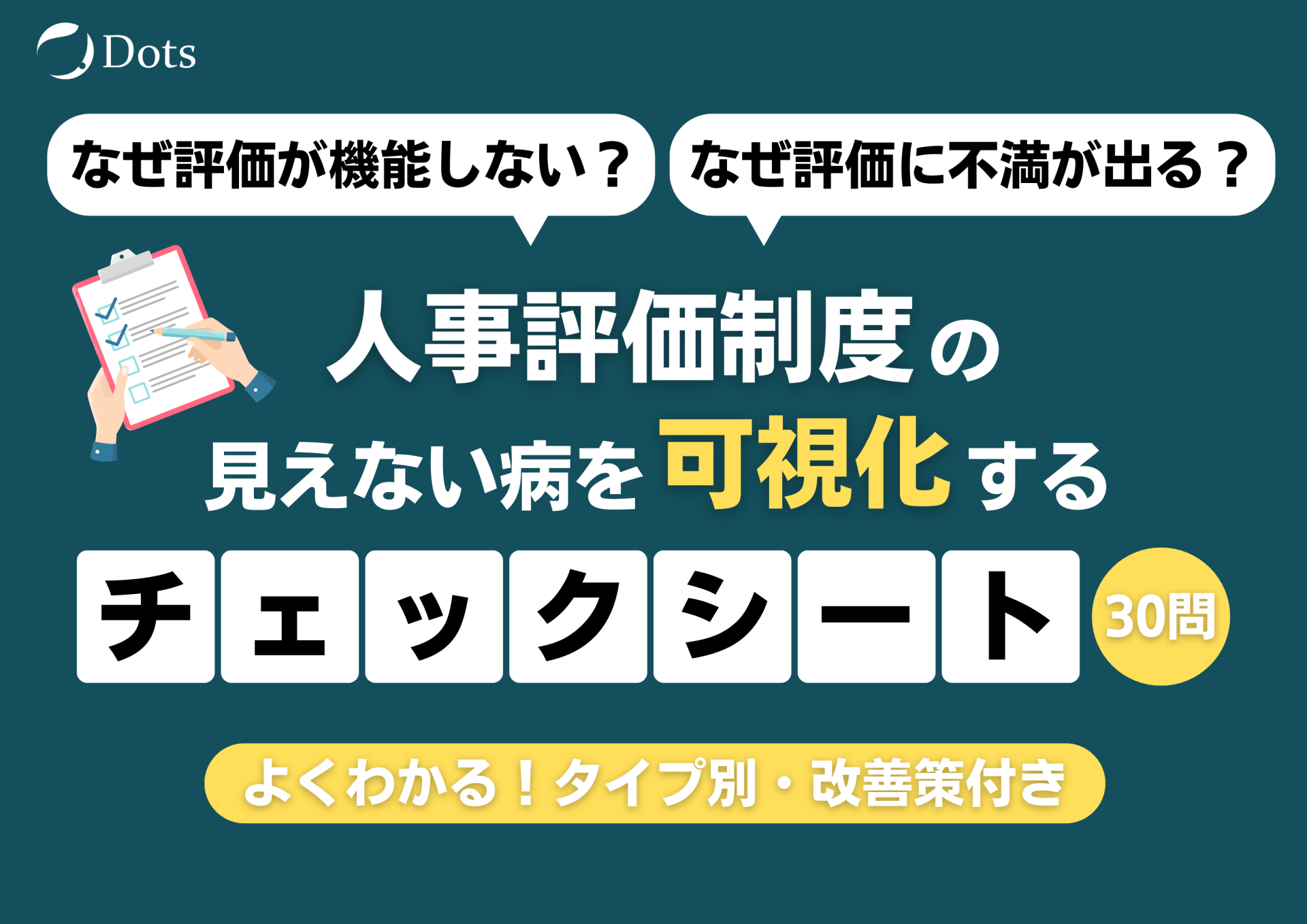


Dots編集部のコメント
最低賃金の引き上げは、私たち国民の暮らしを支えるうえで大切ですが、同時に企業にとっては大きな負担になることもあります。給料が増えても、勤め先の経営が苦しくなれば安心して働き続けられません。
だからこそ、賃金だけに頼らず、働きやすさややりがいといった環境づくりが重要です。最低賃金の議論は「人をどう活かすか」という視点を改めて考えるきっかけになるのではないでしょうか。