40代・50代の再評価が始まった|企業が進める氷河期世代の賃上げと採用強化
ブログ
2025.07.18
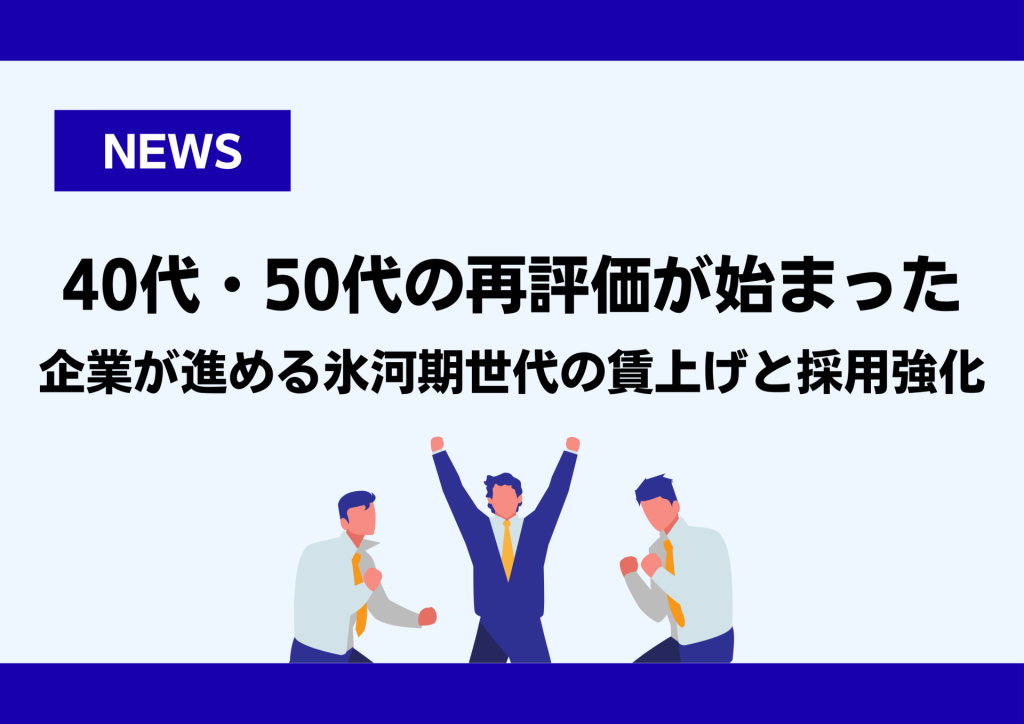
就職氷河期にあたる40代・50代の社員に対して、企業が賃金や採用の見直しを進めています。
セコムやレオパレス21などの企業は、中高年層の管理職に対して賃上げを行い、待遇を改善し始めています。本記事では、その具体的な事例や背景をわかりやすく紹介します。
働く意欲とスキルを持つ中高年層を正当に評価することが、企業の人材戦略や成長にとってますます重要になっています。
40〜50代の賃上げが進む背景とは?
「若手ばかりが優遇されて、自分たちは置き去りにされている」
そんな不満を抱く中高年層に、ようやく変化の兆しが見えています。セコムやレオパレス21といった大手企業が、40〜50代を中心とした管理職層への賃上げを進めているのです。
たとえばセコムでは、2025年7月から管理職手当を平均で約3割引き上げ、年収では約40万円の増加を実施しました。全体平均の賃上げ率が4.35%に対して、管理職層では約8%と大きな差があります。これは、処遇のバランス是正と人材定着を狙ったものです。
またレオパレス21でも、高評価の管理職を対象に最大6%の年俸アップを行いました。非管理職の初任給引き上げなどで賃金逆転の懸念が出ていたため、「管理職として働く意義と魅力を再認識してもらいたい」という意図があります。
こうした動きは、一時的な施策ではなく、世代間の賃金バランスを見直すための中長期的な戦略の一環です。若年層との賃金ギャップに悩む中高年社員のモチベーションを高め、離職防止につなげる企業の姿勢が明確になっています。
企業が注目する氷河期世代の活用と採用強化
人手不足の深刻化により、企業が積極的に注目し始めたのが“就職氷河期世代”の人材です。かつて正社員としての就職が難しかったこの世代は、現在40〜50代となり、実務経験や責任感を備えた即戦力として再評価されています。
警備会社ALSOK埼玉は、2025年度の採用から正社員の応募年齢を従来の44歳から、定年直前の59歳まで引き上げました。これは採用難への対応でもありつつ、「正社員になれたからこそ頑張りたい」という意欲的な応募者が多いという実感が背景にあります。
総合物流の山九も、この流れに積極的です。2022〜2024年度にかけて、183人の氷河期世代を採用。配属先はプラント建設、物流業務、メンテナンスなどで、即戦力としての活躍が期待されています。中には管理職へと昇進した社員もおり、企業側としても高く評価しています。
このような動きは、「経験ある人材の活用」と「現場力の強化」の両立を実現するものです。さらに企業は、氷河期世代の“定着率の高さ”や“意欲の強さ”にも注目しており、採用戦略の中核に据えようとしています。

中高年層の賃金格差と離職リスク
一方で、若手への賃上げが先行したことで、40〜50代の賃金伸びが相対的に鈍化している現実があります。経団連の調査では、2024年の賃上げ配分は「30歳以下中心」が約35%に対し、「45歳以上を重視」はたった1%という偏りが浮き彫りになっています。
また、第一生命経済研究所によると、2020〜2024年の名目賃金上昇率は20代が10%以上である一方、40代は5%台にとどまり、50〜54歳では2.4%も賃金が減少しています。こうした賃金格差は中高年の意欲低下やキャリアへの不安を招き、転職への動きも顕著です。
実際、転職サイト「doda」への45〜60歳の登録者数は、2024年に前年比18%増加。クレイア・コンサルティングには「中高年の処遇改善を相談したい」という声が相次いでおり、年齢だけに頼らない公正な評価制度が求められています。
再評価される中堅社員、職場での存在感とは?
単に賃上げ・採用にとどまらず、企業は中堅社員の「職場での存在価値」にも注目しています。セコムでは、管理職の負担感が見え始めたこともあり、待遇改善に踏み切りました。これにより、管理職のロールモデルが明確化され、若手のキャリア意欲向上のきっかけにもなっています。
同じく管理職と一般職の賃金逆転を避ける観点から、JVCケンウッドでは「一般職の賃金が管理職を上回らないように調整」するなど、処遇の均衡を図る取り組みが進んでいます。これらは、組織内の信頼・公平感を高め、人材定着の土台となる施策です。
キャリア再構築へ、企業と本人の学び直し支援
変化の時代だからこそ、40〜50代のスキル再構築も重要です。独ボッシュ日本法人では、40歳を迎える社員に向けて「キャリア投資」をテーマにした研修プログラムを実施。資格取得や部署異動の目標設定をグループディスカッションで行い、自律的なキャリア設計を促しています。
パソナグループの中高年向け支援サービス「パソナマスターズ」では、40歳代後半〜50歳代の登録者数が過去5年間で約5倍に増加。多くのミドル世代が、学び直しによって新たな職種に挑戦したり、業界転向の道を模索するようになっています。
WHI総研・伊藤裕之所長は、「氷河期世代はキャリア構築の機会を制限されてきたが、リカレント教育や経験を生かせる取り組みによって、再評価・賃金向上が期待できる」とコメントしています。
未来への投資としての“中高年人材戦略”
総じて、これらの動きは“単なる賃上げや採用策”に留まらず、中高年人材を企業成長の中心に据える戦略として位置づけられています。氷河期世代は経験と忠誠心を併せ持つ存在であり、適切な教育・待遇があれば、企業の競争力強化に直結します。
今後は「年齢ではなく、能力と成果に応じた処遇」の実現が鍵となります。賃金制度の見直し、キャリア支援、処遇バランスの調整など、多面的なアプローチを通じて、企業と社員がともに成長していくことが期待されるでしょう。
参考:企業も氷河期対策、セコムなど賃上げ手厚く 中高年も離職リスク―日本経済新聞





Dots編集部のコメント
若手が優遇されがちだった中で、ようやく40〜50代のキャリアや処遇にも光が当たり始めたことに安心感があります。これまで現場を支えてきた世代がきちんと報われることで、組織全体のバランスも整うと思います。年齢に関係なく、努力やスキルが正当に評価される会社がもっと増えることを期待します。